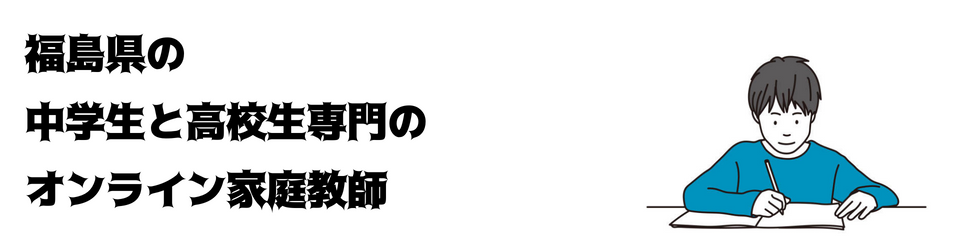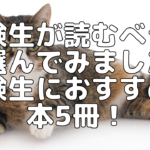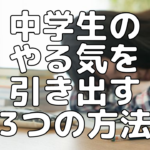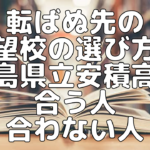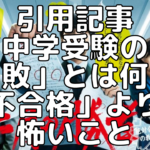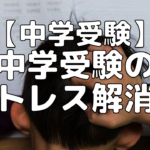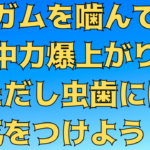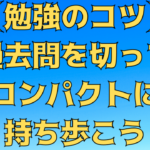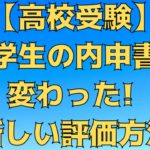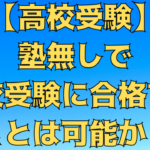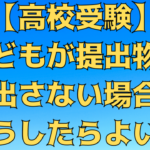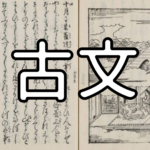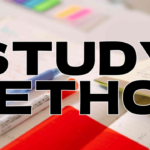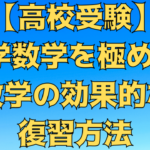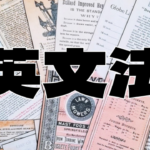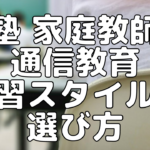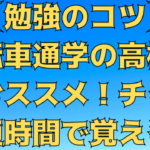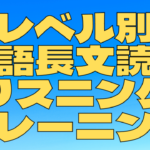2022/08/25
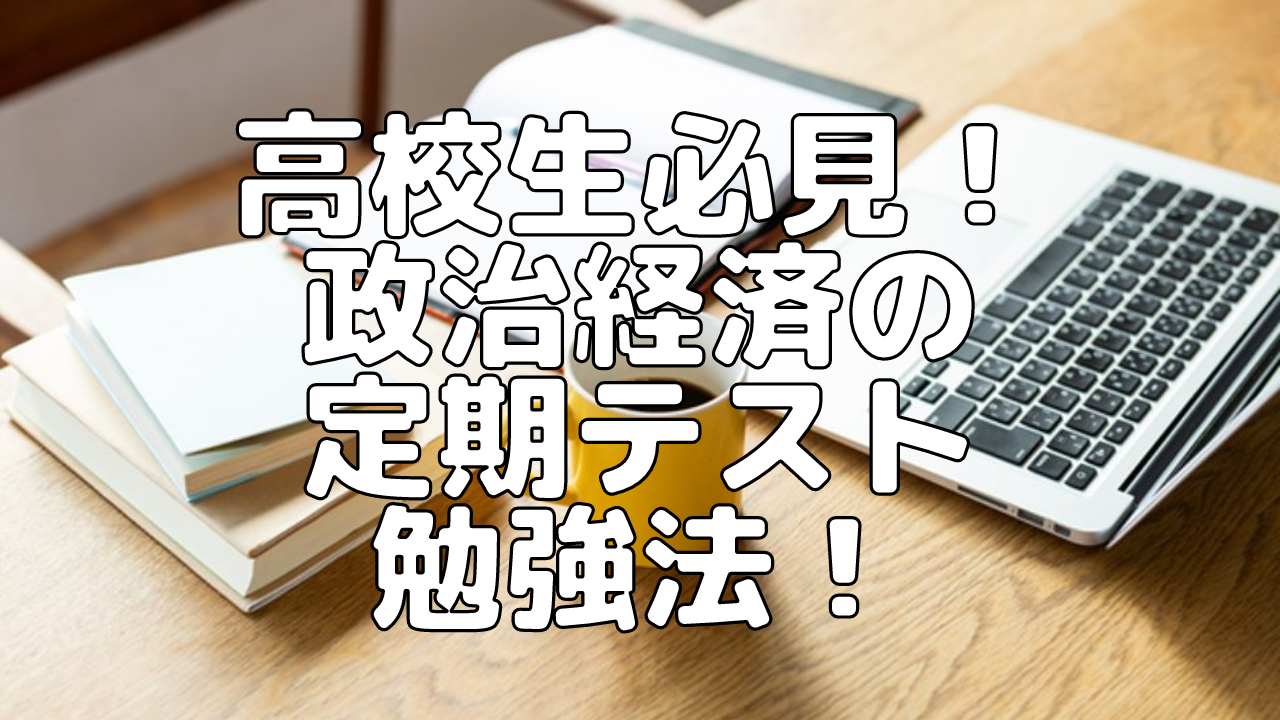
目次
政治経済の勉強量は多くない!
世界史や英語を勉強しなければならない量は膨大です。しかし、これらの科目と比較すると、政治経済学の学習量は決して多いとは言えない。要点を押さえて覚えれば、勉強量も減ります。政治経済の勉強量に臆することはありません。
ニュースを見ることが勉強になる!
政治学はニュースを見ること!ネットニュースや新聞で取り上げられる話題は、政治経済の内容に直結している。教科書をずっと読んで勉強するのは疲れるじゃないですか。教科書をずっと読んでいるのは楽しいものではありません。こんな時は、息抜きとしてネットニュースや新聞で政治経済のコンテンツをインプットすることをお勧めします。これは新鮮なだけでなく、ちゃんと勉強にもなります。政治経済の勉強と並行して、ニュースも読んでみてください。
定期テストの勉強は受験につながる!
受験勉強は、ゼロから作り上げるものではありません。大学入試は高校で習ったことしか出ませんから、定期テストの勉強はもちろん受験につながります。さらに、国語や英語・歴史の科目が有利になる傾向がありますが、定期テストごとに政治経済も勉強しないと、試験中の勉強時間の確保が難しくなります。そのため、受験勉強を始めるときにゼロから始めるのではなく、定期試験中に少しずつ勉強の幅を広げていくことで、受験勉強の負担を軽減することができるのです。定期試験の勉強をただ定期試験の勉強として考えるのではなく、大学受験も視野に入れた勉強を考えてください。
政治経済の定期テストで高得点を取るための勉強法
(1) 試験に直結する情報収集を徹底する
試験について何も知らなければ、何をどれだけ勉強すればいいのか、どこから出題されるのか、正確に知ることはできません。そのため、試験に関する情報を集めることで、やるべきことがより具体的に見えてきます。先生が「ここがテストに出ます」と言ったら、そこをやらなければならないし、「ここは問題ない」と言われたら、そこまで注力する必要はない。このように、具体的に何を勉強すればいいのかを理解するために、先生の話や重要なプリントを集めて、テストに直結する情報をすべて集めよう!というのが、今回の勉強法です。
(2)テストにおける目標を設定する
目的によって、勉強する内容は変わってきます。満点を取りたい、平均点以上を取りたい、苦手な科目でも平均点を取りたい、などなど。目標は人によって、また対象者によっても異なると思います。目標を設定することで、その試験期間にどこで勉強するかが決まります。だから、勉強を始める前に、試験の目的を決めましょう!。
(3) 教科書を読む。
次は、教科書を読むことです。授業や定期テストの内容は、基本的に教科書に準拠しています。ですから、教科書を読むのはとても効果的です。全体像を把握するために、教科書のテストの範囲を読むとよいでしょう。また、いくら教科書を読んでも、理解しにくい内容も出てきます。これらのセクションを理解するために、適宜、先生に尋ねてみてください。
(4)テスト範囲の用語を暗記する
テスト勉強をしていると、漠然とした不安を感じることがありますよね。そんなときは、ノートや小テストを見て、まだ理解できていないことを確認しましょう。暗記は、一問一答の練習問題を使うといいと思います。一問一答は、必要な情報がわかりやすく書かれているので、覚えやすいと思います。また、経済用語は漢字で書くと難しいものもあるので、出てきたら書けるかどうか確認しましょう。試験範囲内の用語はしっかりと覚えておきましょう。
(5)試験前日に自分の弱点をピンポイントで確認
前日に自分の弱点を確認しよう。いくら勉強しても、自分の苦手な分野は必ず出てきます。試験の前日や前々日に自分の苦手な分野を見るだけでも、非常に効果的です。前日に自分の苦手な分野を洗い出し、確認して覚えておきましょう。
うちの子の成績が全然上がらない…そんなお悩みをお持ちではありませんか?間違った勉強法を続けていては成績は上がりません。正しい勉強法に変えるだけで成績は面白いほど伸びていきます。勉強ができないのは、頭が悪いわけでも、才能がないわけでもありません。間違った勉強法で勉強をしてしまってるだけなのです。実際に正しい勉強法に変えてくれた生徒たちは、定期テストや実力テスト、新教研もぎテストの点数がアップしています。
正しい勉強法を知り、実践すれば成績アップは簡単です。マンツーマンの個別指導で自己ベストを更新し続けてみませんか?
駿英家庭教師学院専任講師による授業で成績アップ!
大切なお子様の学習指導は、駿英家庭教師学院にお任せください
- 小中一貫校の中学校受験
- 中学生の高校受験対策
- 高校生の大学受験対策
- 高校生の看護学校受験対策 など
経験豊富な講師陣がお子様の夢の実現をお手伝いいたします
お問い合わせはこちら↓まで