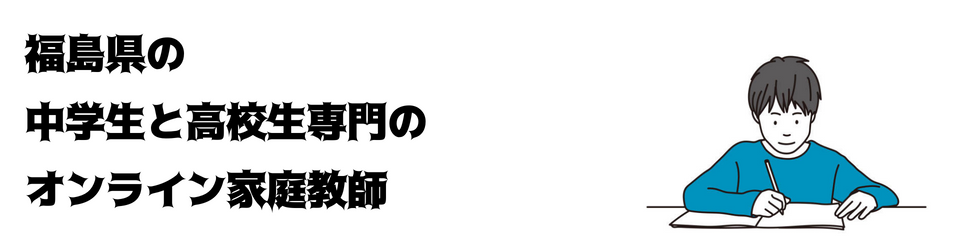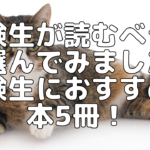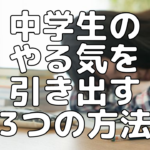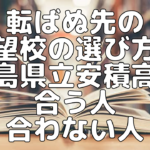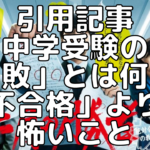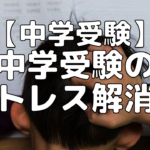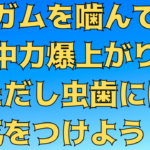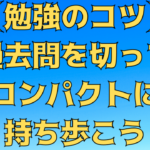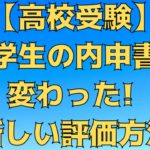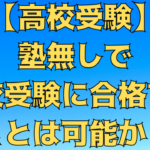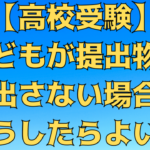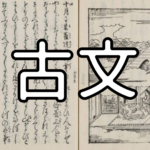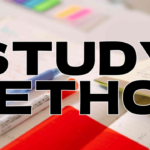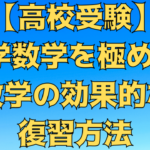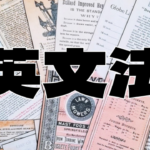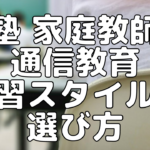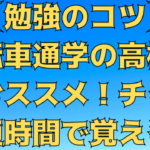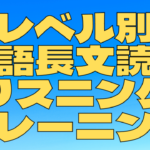2022/08/25
みなさんこんにちは,
郡山家庭教師学院です。
今回は,偏差値と受験校の決め方についてお話します。
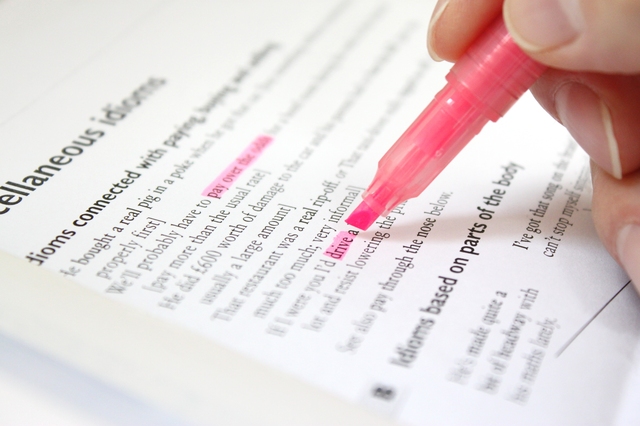
受験する高校を決める最も重要なポイントは偏差値です。
ただ,偏差値だけで受験する高校を決めてしまうと,
不合格だった場合はもちろん,
合格した場合でもひどい目に会うことがありますので,注意してください。
中学3年生の冬休みとなると,
いよいよ受験校を決める時期となります。
ほとんどの生徒が自分の偏差値をもとにして
受験校を決めることになると思いますが,
偏差値の数値だけで受験校を決めることは絶対にしないでください。
受験校を決めるポイントは次の3つです。
1.偏差値
2.3年1学期からの偏差値の推移
3.これまでの自分の勉強量
それぞれについて説明しましょう。
1.偏差値
受験校を決める大切な指標となる偏差値。
各高校には,
合格に必要な偏差値のボーダーラインがあります。
例えば,福島県の県中地区で人気のある
安積黎明高校であれば,
偏差値63~64がボーダーラインです。
ボーダーラインは,
これくらいの偏差値の人は60%の確立で合格できる
と言う意味ですので,
偏差値60でも安積黎明高校に合格する人はいます。
しかし,自分の偏差値が
志望校のボーダーラインよりも2~3低い場合,
その高校は受験しないほうがよいでしょう。
もちろん,ボーダーラインと比較して2~3低い程度では,
合格の可能性は十分にあります。
ただ,合格できたとしても,
その高校では下位グループです。
それでもよいですか?
・入学してから死ぬ気で勉強をがんばる覚悟がある。
・推薦による大学入試は考えていない。
・絶対に入りたい部活がある。
などのように,
その学校の下位グループからのスタートとなっても
まったく問題がなければ,この限りではありません。
2.3年1学期からの偏差値の推移
自分の偏差値の推移も,
受験校を決めるにあたっては重要です。
・自分の偏差値の平均が志望校のボーダーラインである。
・自分の偏差値のワーストが志望校のボーダーラインである。
このような生徒の場合,
志望校を受験する価値は十分にあると思います。
油断は禁物ですが・・・。
・自分のベストの偏差値が志望校のボーダーラインである。
このような生徒の場合,
志望校を受験するのは危険です。
受験本番でベストの結果を残すことができればよいですが,
少しで調子が悪ければ,
不合格と言う可能性も十分にあるわけです。
ベストの偏差値が2学期末~3学期初めにかけて出ていればよいのですが,
夏休み前の模試がベストの偏差値で,
その後はダダ下がり,と言う場合は,
ワンランク低い高校へ受験校を変更しましょう。
3.これまでの自分の勉強量
最後に自分の勉強量を振り返ってみましょう。
死に物狂いで勉強をして,
必死の思いで志望校のボーダーラインぎりぎりに到達したのであれば,
その高校を受験するには,再考の余地ありです。
何とかその高校に合格することができたとして,
中学校3年の時以上の勉強量を,
その後の3年間続けていくことができますか?
高校に合格することはゴールではありません。
スタートです。
必死の思いでぎりぎり合格した高校で,
それなりのポジションをキープしていくためには,
その必死の勉強以上の勉強を3年間続けていかなければなりません。
それができなければ,必ず落ちこぼれます。
これが大学入試や,就職試験であれば,
必死に勉強して,ぎりぎり合格でもかまいません。
しかし,大人になるための中間地点である高校受験で,
燃え尽きてしまうのは早すぎます。
ある程度の余裕を持って,高校入学後の生活を送るためには,
必死の勉強でぎりぎりの合格では厳しいでしょう。
無理をしているとどこかに歪が出てきます。
自分が生き生きと,自分らしさを発揮できる高校で
充実した高校生生活を送るほうがよいと思います。
偏差値レベルでは一段下の高校であっても,
部活や学業をがんばれば,
推薦でレベルの高い大学に進学することができるかもしれません。
ぎりぎりでレベルの高い高校に入学したのでは,
そんなことは到底できませんからね。